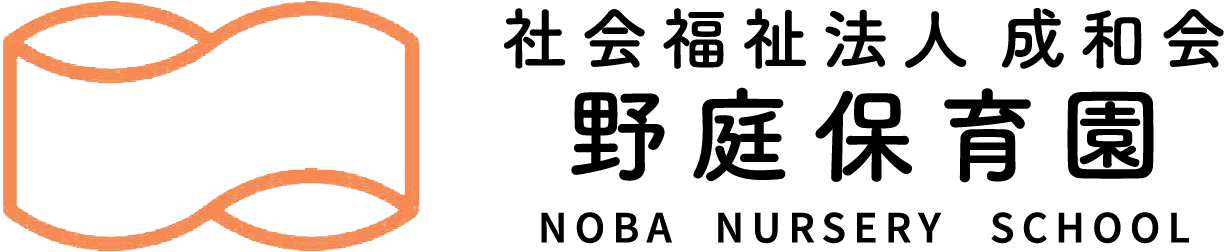子どもたちの自主性と創造性を引き出し、
身体・情緒・社会性を
バランスよく育てていきます。
野庭保育園では、保護者の方のお仕事や出産などの事情に伴い、
家庭において保育することができない乳幼児のお子様を
単にお預かりするのではなく、一人ひとりが持っている力を
いろいろな場面で発揮できるよう、子どもたちの自主性と創造性を引き出す
体験・保育・教育を行なうことを念頭に置いています。
そして、何よりも大切にしているのが日々のなにげない「遊び」を通じて、
かけがえのない「学び」を届け、豊かな人間形成に寄り添っていくことです。
そのために当園では独自の保育目標を設け、
日々の取り組みや保育士の人財育成に力を入れています。


保育目標
1
健康な体をつくる保育
日々の健康と体づくりは、保育の基本です。中でも食育は、健康な体の根本と言えます。そこで当園の給食では、極力化学薬品が使われていない自然な食材を選んでいます。さらに畑での野菜づくりを行なっており、子どもたちが自分で食物を育て、収穫し、食べるまでの体験も食育の一環として行なっています。そして、健康な体づくりでもうひとつの基本が運動です。当園では、年少から年長を中心に保育士の専門的なサポートのもとで元気よく走ったり、遊具で遊んだりしながら体の使い方を学んでいきます。0歳から2歳までの子どもたちは室内遊具で体の使い方を学びます。たとえば、0歳児なら平らな場所だけでなく坂をハイハイすることでバランスの取り方や安全な転び方が自然と身についていきます。
2
遊びを充実させる保育
子どもたちが楽しいと思うだけでなく「学び」に満ちていること。それが私たちの考える「遊び」の充実です。遊び方を与えられるだけでなく自ら考えて創造力を広げていくことが大切で、その考えは中央に広いスペースを確保し、遊具は周囲に置いている園庭の景色にも反映されています。例えば子どもたちが鬼ごっこをしたいと言ったら、まずはみんなで鬼ごっこを楽しみます。そのうちに、しっぽお尻につけたしっぽ取りゲームというアイディアが出たら、保育士がしっぽを用意して渡します。室内でもお絵描きのときに白い紙だけでなく、カラーの紙を用意することで子どもたちの選択肢を広げたり、お散歩で拾った四季折々の葉っぱや木の実を造形の材料にします。「遊び」の充実は、想像力の充実でもあるのです。

3
思いやりの心を
育てる保育
私たちの保育にとって思いやりの心は、0歳児から年長までの年齢に応じて時間をかけて育んでいくものです。子どもたちは自我が芽生えるとイヤイヤ期を経て、ようやく自分自身がやってほしいことを伝えられるようになっていきますが、それぞれの時期に合わせて思いやりを伝えていくことで心はゆっくりと、豊かに育まれていきます。そして、当園では相手が子どもであっても、いえ、子どもだからこそ一人の人間として接することを徹底しています。正しい言葉づかいや感謝を表す大切さは、その基本です。また、子ども同士のトラブルがあっても、「注意して終わり」にはしません。トラブルは、思いやりの心を学ぶ絶好のチャンス。プロとして保育士が見守りながら、子どもたちが自ら考えて思いやりの心にたどり着けるように寄り添っていきます。

4
「できた」という
達成感で
自身を育む保育
小さな成功体験は、子どもたちに確かな自信を与えてくれます。その積み重ねはやがて大きな自信となり、自分を信じる力へと変わっていきます。だからこそ、最初の「やってみよう」を引き出し、「できた」を繰り返すことを私たちはとても大切にしています。象徴的な例が、跳び箱です。いきなり段が高すぎると、興味さえ失ってしまうので、まずは必ずできる高さから始めます。しかしさらに高い段を跳ぼうとすれば助走をつけなければいけません。それが、走ることの練習へとつながっていきます。跳び箱は子どもたちにとって一番身近な恐怖かもしれませんが、段階的に越えていけば最終的には大きな段も越えていけるのです。ときにはできないときがあっても保育士がプロとしてサポートし、子どもたちの中に挑戦する心を育んでいきます。

園の特色
プール
子どもたちが大好きなプールです。水遊びを通して、子どもたちの感覚は磨かれていきます。水の心地よさを感じるのはもちろんですが、太陽の光が水面に反射しキラキラした美しさや、自由に形を変える水の不思騰さなどは好奇心や探究心が刺激されます。また水をバシャバシャさせて音を楽しむなどの、五感を育てながらプールを楽しんでいます。

畑
園庭の花壇を利用して小さな畑を作っています。5 月になるとさつま芋の苗を植えて収穫そしてクッキングなど、一連の流れから食に興味を持ち自然に触れる経験をしています。さつま芋栽培や収穫を通して責任感や達成感を経験し、いろいろなことに気付き、感性をより豊かにしています。収穫をしたさつま芋はクッキングでおやつを作りみんなで食べています。

木のおもちゃ
プラスチックにはない、木の「ぬくもり」。木のおもちゃは手で触ったときにプラスチックよりあたたかく感じます。さらに、プラスチックとは違う滑らかな手触り・香り・木目の模様などを通して、五感が育まれていきます。
木のおもちゃはシンプルな作りのものが多く、プラスチックのおもちゃのようにボタンひとつで音が鳴る・動く・光るといった仕掛けがありません。そのため「どうやって遊んだら面白いかな?」と子どもが自分で考えて遊ぶ必要があります。先生やお友だちと一緒に遊びながら新しい遊び方を考えることで、想像力・創造力が自然と鍛えられていくのです。

保育目標を
達成するために
〜取り組みの方向性〜
アイディアを
取り入れる保育
「できた」という達成感を得るために、絵画コンクールへの出品や老人会への表敬訪問など、第三者に評価してもらうアイディアを取り入れています。また、体を丈夫にする活動プランなども心がけています。
遊びから学びへ
つなぐ保育
例えば、どんぐりを拾ったとき、数字に興味を示す傾向が感じられたら、「何個とれた?」「いっしょにしたらいくつかな?」と語りかけるなど、あらゆる出来事にチャンスを探し、「遊び」から「学び」へつなぐ保育を心がけています。
保育者の資質向上
保育を通じて人間形成を目指す際、保育士自身の人間性とプロとしての向上心が欠かせません。私たちは、研修と実習を通じて保育士自身の「学び」を大切に考え、常に資質の向上に取り組んでいます。